出産のお金がない方へ|妊娠中や出産後にもらえる補助金・公的制度やローンを紹介
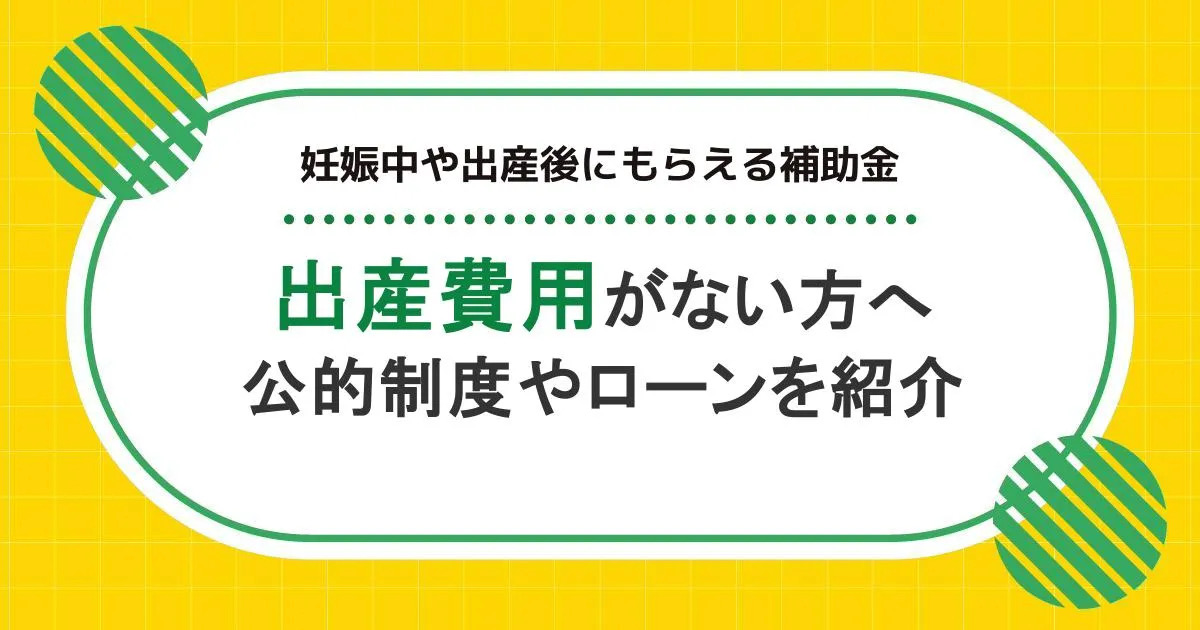
出産費用は高額になるため、出産を控えている人のなかには、金銭面で不安を感じている人もいるかもしれません。しかし、公的制度を活用することで、出産費用を抑えることが可能です。
たとえば、出産育児一時金は1児につき最大50万円が支給されます。直接支払制度や受取代理制度を利用すれば、医療機関での支払いは出産育児一時金の超過分のみとなるため、自己負担額を大きく減らすことができます。
この他にも、妊娠中や出産後の生活を支援するための公的制度が用意されているため、事前にどのような制度が利用できるかを確認しておきましょう。
- 出産や育児に関する補助金や助成金の支給を受けるには、自治体や健康保険組合での申請が必要です。
- 健康保険組合に加入している場合は、「出産費貸付制度」を利用して、出産費用を無利子で借り入れることも可能です。
- 出産や育児費用をサポートするために各自治体が独自の制度を設けている場合もあります。
目次
OPEN出産のお金がないときはどうすればいい?まずは補助金を検討しよう
妊娠、出産にかかる費用は高額になるため、経済的な不安を感じるかもしれません。しかし、国や自治体が用意している公的制度を利用することで、出産にかかる費用の一部を補うことができます。代表的な支援策として「出産育児一時金」や「高額療養費制度」などがあり、これらを活用すれば、自己負担額を抑えることが可能です。
公的制度の詳細は「出産・育児でもらえる補助金や助成金【公的制度】」で解説しています。
出産にかかる費用はいくら?
厚生労働省の「出産費用の状況等について」によると、正常分娩における平均出産費用は約51.8万円(令和6年度上半期時点)です。出産費用は年々増加傾向にあり、家計への影響も大きくなっています。
正常分娩の出産費用の内訳を見てみましょう。
| 入院料 | 125,671円 |
|---|---|
| 分娩料 | 306,327円 |
| 新生児管理保育料 | 51,887円 |
| 検査・薬剤料 | 16,308円 |
| 処置・手数料 | 17,759円 |
参考:出産費用の状況等について|厚生労働省
※令和6年度上半期時点
個室を利用した場合や特別なサービスを受けた場合は追加費用が発生します。帝王切開や無痛分娩の場合、追加で数万〜数十万円程度の費用がかかることもあるでしょう。
また、実際にかかる費用は、地域や医療機関によって大きく異なります。たとえば、「正常分娩の都道府県別の平均出産費用(令和5年度)」によると、平均出産費用が最も高いのは東京都で625,372円、最も低いのは熊本県で388,796円となっており、約24万円の差が出ていることがわかります。
出産費用は健康保険の適用外!自分で負担する必要がある
2025年5月時点では、妊娠や出産にかかる費用は健康保険の適用外となっています。健康保険は本来、病気やケガの治療に対して適用されるものですが、妊娠や出産は病気ではなく生理的な現象とみなされるためです。
ただし、帝王切開や早産分娩など、医療的な処置が必要な異常分娩の場合は健康保険が適用され、費用の一部が保険でカバーされます。また、政府は2026年度を目途に正常分娩の健康保険適用を検討していますが、現時点では適用されていません。
このように、出産費用の大部分は自己負担となるため、事前に公的制度や助成金について把握し、計画的に準備を進めることが大切です。
出産・育児でもらえる補助金や助成金【公的制度】

※2025年5月時点
ここでは、出産や育児に関する公的制度について、対象者や支給額、申請方法などを説明します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険の被保険者、または被扶養者が出産した際に支給される制度です。妊娠4ヵ月(85日)以上の出産が対象となります。
出産育児一時金の概要
- 対象者:健康保険や国民健康保険の被保険者または被扶養者
- 支給額:1児につき最大50万円(※)
- 支給時期:出産時
※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合の支給額は48.8万円です。
出産育児一時金の申請方法は次の3つがあります。
| 申請方法 | 詳細 |
|---|---|
| 直接支払制度 |
医療機関が健康保険組合などに申請し、 出産育児一時金が医療機関に直接支払われる |
| 受取代理制度 |
被保険者が医療機関に事前に申請し、 出産育児一時金が医療機関に支払われる |
|
上記の制度を 利用しない場合 |
出産費用を自己負担し、後日、被保険者が 健康保険組合に申請書を提出する |
直接支払制度や受取代理制度を利用すれば、医療機関の窓口での自己負担額は、出産育児一時金を超える金額のみとなります。これらの制度を利用できるかどうかは、出産予定の医療機関に確認しておきましょう。
出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金の概要
- 対象者:申請する自治体に住民票がある妊婦および産後一定期間内の保護者
- 支給額:妊娠時、出産後に各5万円相当(合計10万円相当)
- 支給時期:妊娠時・出産時
- 申請方法:自治体により異なる
「出産・子育て応援交付金」は、妊娠時と出産後にそれぞれ5万円ずつ、合計10万円相当の支援が受けられる制度です。支給方法は、現金や商品券など自治体によって異なります。妊娠届や出生届を提出し、所定の面談などを受けることで支給されます。
申請方法や必要書類は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口やWEBサイトで確認しておきましょう。なお、この制度とは別に、自治体独自の支援制度が用意されていることもあります。
出産手当金
出産手当金の概要
- 対象者:健康保険の被保険者で、出産による休職中に給与を受けていない人
- 支給額:標準報酬日額の3分の2相当
- 支給時期:出産予定日の42日(多胎妊娠は98日)〜出産翌日56日後の給与未支給期間
- 申請方法:健康保険組合に「出産手当金支給申請書」を提出
出産手当は、出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けなかった場合に支給される制度です。対象期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産翌日以降56日までとなっています。出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた日数分も支給の対象となります。
支給額は、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した金額の3分の2です。勤務先経由で健康保険組合に申請することが一般的ですが、被保険者本人が申請することも可能です。
傷病手当金
傷病手当金の概要
- 対象者:健康保険の被保険者で、業務外の病気やけがで就労不能となり給与がない人
- 支給額:標準報酬日額の3分の2相当
- 支給時期:会社を連続して3日間休んだ後の4日目〜最長1年6ヵ月
- 申請方法:勤務先経由または被保険者本人が健康保険組合に支給申請書を提出
傷病手当金は、業務外の病気やけがにより働けなくなった際に、健康保険の被保険者が収入の一部を補填するための制度です。たとえば、切迫流産や悪阻(つわり)などで仕事を休まざるを得ない場合にも対象となります。
支給は、療養のために会社を連続して3日休んだ日が連続して3日あること(待機期間)を条件に、4日目以降の仕事を休んだ日に対して行われます。休業期間中に給与の支払いがある場合はその分が減額され、給与の支給額が傷病手当金より多い場合は支給されません。
また、出産手当金と支給期間が重なる場合は、原則として出産手当金の支給が優先されます。ただし、傷病手当金の支給額が多い場合は、差額分のみが支給されます。
申請は、勤務先を通じて行うことが一般的ですが、被保険者本人が健康保険組合に直接「傷病手当金支給申請書」を提出することも可能です。
育児休業給付金
育児休業給付金の概要
- 対象者:雇用保険の被保険者(1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した人)
- 支給額:休業開始から180日までは休業開始前賃金の67%、181日目以降は50%
- 支給時期:原則として育児休業開始の翌月以降、2ヵ月ごとに支給
- 申請方法:勤務先経由または被保険者本人がハローワークに支給申請書を提出
育児休業給付金は、育児休業中の収入を補填し、子育てと仕事の両立を支援するための制度です。雇用保険に加入している被保険者が育児休業を取得し、一定の要件を満たすことで支給されます。出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金を総称して「育児休業等給付」といい、育児休業給付金はその一部です。
育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳になるまでですが、保育所に入れないなどの事情がある場合は、最長で子どもが2歳になる前日まで延長できます。
勤務先が申請手続きを行うことが一般的ですが、被保険者本人が手続きすることも可能です。申請時には、申請書の他、賃金証明書や、賃金の額と支払状況、所定労働時間などを確認できる書類が必要です。
児童手当
児童手当の概要
- 対象者:0歳から高校卒業まで子を養育する保護者
- 支給額:子ども1人につき毎月15,000円〜30,000円
- 支給時期:子どもが0歳から高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
- 申請方法:出生日翌日から15日以内に市区町村(公務員は勤務先)に申請
児童手当は、0歳から高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯に支給される手当です。出産にかかるお金ではありませんが、出産後に申請が必要になるため、覚えておきましょう。
支給額は所得にかかわらず、3歳未満は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上の高校生年代までは月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。
児童手当の支給を受けるためには、出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)への申請手続きが必要です。
出産にかかる費用を抑えられる制度
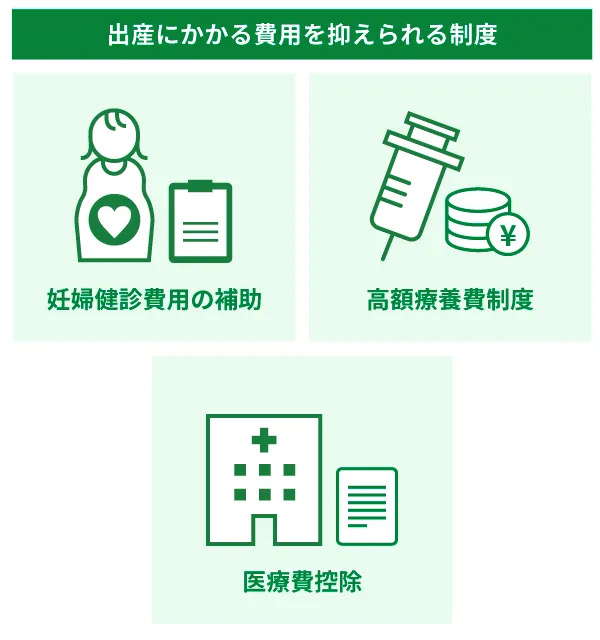
ここでは、出産にかかる費用の負担を軽減できる公的な制度を紹介します。
妊婦健診費用の補助
妊娠中は母体と胎児の健康を守るために定期的に受診が必要ですが、その費用は自己負担となる場合、経済的に負担になるかもしれません。しかし、多くの自治体では、妊婦健診費用の一部を助成する制度を設けています。
母子健康手帳の交付時に妊婦健診費助成券が交付され、指定の医療機関や助産所で健診を受ける際に助成券を提出すると、助成額を差し引いた金額のみの支払いで受診できる仕組みです。助成回数や上限金額は自治体によって異なります。
母子健康手帳を受け取る際に案内されるため、詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認してみましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療費が高額になった場合、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。自然分娩で出産した場合は高額療養費の対象外ですが、帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩など医療行為があった場合は高額療養費の対象となります。
高額療養費制度を利用する場合の自己負担限度額(月額)は、年齢や年収によって異なります。69歳以下の人の自己負担限度額(月額)は次のとおりです。
|
適用区分 (年収目安) |
月の上限額 |
|---|---|
| 約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 約770万円〜1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 約370万円〜770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 〜370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※2025年5月時点
なお、1つの医療機関での自己負担額が上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関での自己負担額を合算して上限額を超える場合は、高額療養費の支給対象です。
加入している公的医療保険(健康保険組合や市区町村国保など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
医療費控除
年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の負担を減らすことができます。すでに納め過ぎた所得税がある場合は還付金として戻ります。妊娠・出産にかかる費用も対象となる場合があるため、確認しておきましょう。
医療費控除の対象となる費用
- 妊娠診断後の定期検診・検査費用
- 通院費用(電車・バスなど)
- 出産による入院時のタクシー代
- 入院中の食事代 など
医療費控除の対象外となる費用
- 出産のために実家に帰省する際の交通費
- 入院時に必要な身の回り品の購入費(寝巻きや洗面用具など)
- 入院中の出前や外食費 など
なお、出産育児一時金や家族出産育児一時金などの給付金を受け取った場合、その金額を支払った医療費の合計から差し引いて計算する必要があります。
出産にかかる費用を借りられる「出産費貸付制度」
妊娠中、補助金を受け取る前に資金不足になることも考えられます。その場合に検討したい制度として「出産費貸付制度」があります。
出産費貸付制度とは、出産に要する費用が必要である場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子でお金を借り入れられる制度です。妊娠中に急な出費が発生した場合や、補助金の支給まで生活費に不安がある人にとって、大きな助けとなります。
対象者は全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうち、次に該当する人です。
- 出産予定日まで1ヵ月以内
- 妊娠4ヵ月(85日)以上で、病院・産院等に一時的な支払いを要する
出産育児一時金の支給見込額の8割相当額を限度とし、1万円単位で無利子で貸し付けが行われます。
利用する場合は、健康保険組合に出産費貸付金借用書や被保険者証、出産育児一時金支給申請書などの書類を提出します。借入後は、出産育児一時金の給付金を返済に充てて、残額は申請時に指定した金融機関の口座に振り込まれる仕組みです。
利用を検討している人は、加入している健康保険組合の窓口に相談してみましょう。
生活保護世帯・母子家庭向け|出産費用の負担軽減につながる制度
ここでは、生活保護世帯や母子家庭・ひとり親家庭向けに、出産費用や生活費の負担を軽減できる公的制度をご紹介します。
生活保護受給者向け
生活保護を受給している人は、出産や妊娠中、出産後の生活をサポートする扶助や加算があります。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 出産扶助 |
生活保護制度の一環として、出産にかかる費用を支援 支給目的:出産費用、入院費用、衛生材料費などを補填 支給額:基準額が311,000円以内 |
| 妊婦加算 |
妊娠が確認された月から出産月まで、生活保護費に加算 支給目的:妊婦健診の交通費、衣類の購入費用などを補填 支給額(月額):妊娠6ヵ月未満は9,130円、6ヵ月以上は13,790円 |
| 産婦加算 |
出産した月から半年間まで、月額8,480円が生活保護費に加算 支給目的:栄養補給、衛生用品、育児用品の購入費用などを補填 支給額(月額):8,480円 |
| 母子加算 |
ひとり親世帯に対して支給される加算 支給目的:ひとり親世帯の生活費の補填 支給額(※):児童1人18,000円、児童2人23,600円 3人増えるごとに2,900円加算 |
※ 1級地の場合
母子家庭・ひとり親家庭向け
母子家庭やひとり親家庭には、出産後の生活を支えるための手当や貸付制度があります。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 児童扶養手当 |
対象:18歳未満の子を養育するひとり親 目的:生活の安定と自立の促進 支給額:所得や児童の数により異なる |
|
母子父子寡婦福祉 資金貸付金制度 |
対象:ひとり親家庭の父母など 目的:子どもの学費や生活費など |
児童主要手当の支給額は受給者の所得や児童の数によって異なり、全部支給と一部支給があります。
これらの制度を活用することで、出産後の生活や子育てにかかる経済的な負担を軽減できる可能性があります。制度の内容や支給額は年度や自治体によって異なる場合があるため、最新の情報は市区町村窓口や福祉事務所などで確認してみましょう。
出産のお金がないときの対処法【公的制度以外の選択肢】
出産費用をまかなう方法として、公的制度以外にもいくつかの選択肢もあります。状況に応じて、次の4つの手段も検討してみましょう。
家族からの支援を受ける
まず検討したいのが、親や兄弟姉妹など家族からの金銭的な支援です。家族に相談することで、資金を受け取ったり、無利子で資金を借り入れられたりする場合があります。
ただし、金銭の貸し借りはトラブルの原因となることもあるため、あらかじめ返済計画を明確に伝えることが大切です。借りられる場合は、感謝の気持ちを忘れずに、今後の返済やお礼の方法についてきちんと話し合っておきましょう。
医療ローンを利用する
医療ローンは、医療費の支払いに利用できるローンのことです。銀行などの金融機関が提供している目的別ローンのひとつで、一般的なカードローンよりも金利が低めに設定されていることが特徴です。
ただし、医療ローンには審査があり、審査結果によっては利用できない可能性があります。また、返済計画を立てずに利用すると、家計への負担が大きくなるため、事前に返済シミュレーションを行い、見通しを立てて計画的に利用することが大切です。
クレジットカードの分割払いやリボ払いを活用する
医療機関によっては、医療費の支払いにクレジットカードを利用できる場合があります。出産までに現金を準備することが難しいときは、クレジットカードで支払い、分割払いやリボ払いを活用するのも選択肢のひとつです。
ただし、分割払いやリボ払いには手数料が発生するため、現金払いや一括払いに比べて支払総額が多くなる点に注意が必要です。また、クレジットカードには利用可能枠が設定されているため、出産費用をまかなえるだけの枠があるかどうかを、事前に確認しておきましょう。
あわせて読みたい
カードローンとクレジットカードの違いは?審査や借入方法、金利の違いを理解しよう
カードローンを利用する
カードローンは、銀行や消費者金融などの金融機関が提供している個人向けの融資サービスです。すべてのカードローンには審査があり、審査によって決まった借入限度額の範囲内で、繰り返しお金を借りられます。
カードローンは資金使途が自由なため、出産費用はもちろん、通院費や新生活に必要な費用などにも利用できます。ただし、医療ローンと比較して金利が高めの傾向があるため、返済計画を立てて、無理のない借り入れを心がけることが重要です。
あわせて読みたい
カードローンとは?仕組み・メリットデメリット・借入方法をわかりやすく解説
出産・育児のお金をカードローンで借りる注意点
出産や育児にかかる費用は、公的制度が充実しているため、まずは利用できる制度の申請手続きを進めましょう。
それでも資金が足りない場合はカードローンが便利です。ただし、カードローンを利用する前に、知っておきたい注意点が3つあります。
金利と返済総額を把握する
カードローンには必ず金利が設定されており、借り入れた金額に対して利息が発生します。利息とは、借り入れに対する対価として支払う金銭のことです。
利息を決める要素のひとつに「金利」があります。カードローンの金利は金融機関や商品によって異なりますが、年3.0%〜年18.0%程度が一般的です。金利が高いほど、最終的な返済総額が増えやすくなるため、借り入れの前に必ず金利を確認し、返済計画を立てることが重要です。
あわせて読みたい
カードローンの金利とは?仕組みや比較方法、計算方法を解説
希望の借入金額が借りられない可能性がある
カードローンの利用には審査があるため、希望する金額を借り入れられるとは限りません。審査では、申込者の収入や他社からの借入状況などをもとに、総合的に判断されます。
産休・育休中でも申込みが可能な場合がありますが、収入が減少していると借り入れが制限されることもあります。
返済計画を立てたうえで利用する
カードローンは返済期間が長期化すると、その分利息の負担が増え、最終的な返済総額が大きくなります。毎月の返済額や返済期間を事前にシミュレーションをして、無理のない返済計画を立てることが大切です。
また、臨時収入が入った際には繰り上げ返済を行うなど、早期完済を目指す工夫も有効です。
あわせて読みたい
カードローンの返済方法とは|無理なく確実に返済するコツを解説
出産費用の借り入れにも利用できる京都銀行カードローン<ダイレクト>
京都銀行カードローン<ダイレクト>は、入会金・年会費が無料のカードローンです。資金使途は限定されていないため、出産費用や出産後の生活費のための借り入れなどにも利用できます。
パソコンやスマホで24時間365日申込みができ、仮審査の申込時は京都銀行の口座が不要です。
※別途、正式審査のお申込みまでに普通預金口座のご開設が必要となります。
※お申込みは、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、愛知県にお住まいの方が対象です。
契約後は専用のローンカードを持ち歩くことなくATMで借り入れができます。また、スマホアプリでも借り入れが可能です。
京都銀行カードローン<ダイレクト>の借入利率は年1.9%〜年14.5%です。実際に適用される借入利率は借入限度額によって異なり、たとえば借入限度額10万円の場合、借入利率は年14.5%となります。一般的にキャッシングの借入利率の上限は年18.0%前後ですが、京都銀行は借入利率の上限が年14.5%と比較的低いといえます。
※「お借り入れ5秒診断」は借り入れを検討する際の目安であり、実際の申込時の審査結果と異なる場合があります。
※シミュレーション結果はあくまでも簡易的な試算であり、お取引状況により実際のご返済金額やご返済期間と異なる場合があります。(ご返済金額は借入残高に応じて決まるため、ご返済が進み借入残高が少なくなると、毎月のご返済金額は少なくなります。)
出産費用に関するよくある質問
Q.妊娠中ですがお金がなくて不安です。どうすればいいですか?
A.
多くの自治体では、妊婦健診費用の一部を助成する制度を設けています。また、出産費用については、「出産育児一時金」により最大50万円の支援を受けられます。健康保険組合に加入している場合は、「出産費貸付制度」を利用して、出産育児一時金が支給されるまでの間に費用を借り入れることも可能です。
まずはお住まいの自治体に相談し、どのような制度を利用できるか確認してみることをおすすめします。
Q.出産後の生活費が足りません。どうすればいいですか?
A.
出産後の生活費を支援する制度として、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、児童手当などがあります。これらを活用することで出産後の家計負担を軽減できる可能性があります。制度の詳細や申請方法は、市区町村役場のWEBサイトや窓口などで確認してみましょう。
Q.出産までにかかる費用の総額はいくらですか?
A.
出産費用は地域や医療機関によって異なりますが、厚生労働省の「出産費用の状況等について」で公表されている「正常分娩における平均出産費用」は約51.8万円(令和6年度上半期時点)です。
参考:出産費用の状況等について|厚生労働省
また、「出産育児一時金(最大50万円)」で出産費用を大幅にカバーできるため、実質的な自己負担額は少なくなります。妊婦健診や出産準備費用などもかかりますが、自治体の助成制度が利用できる場合があります。
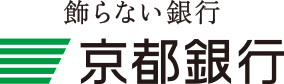

ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者) 他
飯田 道子
出産はいわゆる疾病とは異なるため、かかる費用は自分で準備しなければなりません。出産費用をまかなう方法としては健康保険組合の出産費貸付制度を利用する他、医療ローンやカードローンに申し込むといった選択肢があります。あらかじめシミュレーションをしておき、返済計画をしっかり立てることが必要です。